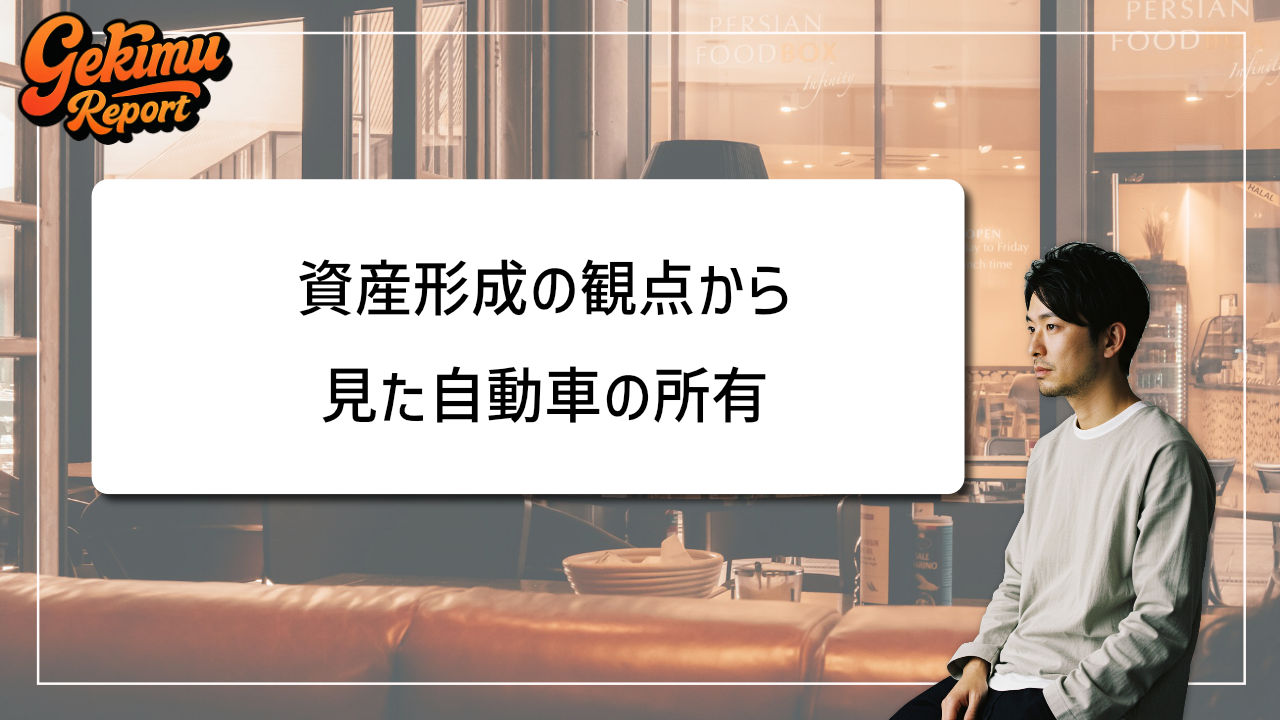都会 vs. 地方:車の必要性と利便性の違い
総じて、都会では「なくても困らない」一方、地方では「ないと困る」というのが車の必要性の大きな違いです。
都市部の状況
- 大都市では公共交通機関が発達しており、日常生活に車が必須でないケースが多く見られます。東京23区のような中心部では、自家用車非保有世帯の割合が高く、特に独身世帯や低所得層、高齢者ではその傾向が顕著です。これは「維持費負担が大きい」ことが主な理由とされ、車を持たなくても電車・バス・タクシーで十分生活できるためです。
- 実際に都心に住み、日常の通勤通学や買い物を公共交通でこなす人にとって、マイカーは贅沢品とみなされることもあり、ファイナンシャルプランナーから「貯蓄を増やしたいなら車は手放しカーシェア等を利用すべき」といった助言がなされるほどです。
- 都市部では駐車場代も高額(東京中心部では月額数万円レベル)で、維持費が家計を圧迫しがちです。そのため「車なし」でも困らないライフスタイルが十分可能であり、むしろ無理に車を所有すると資産形成の妨げになりかねません。
地方部の状況
- 一方で地方では車は生活必需品になるケースが多いです。電車やバスの本数が少なく、徒歩圏に店や病院がない地域では、車がないと日常の移動(通勤・通学・買い物・通院など)に支障をきたします。統計的にも地方圏では世帯あたりの車保有率が高く、都市部より多くの世帯が複数台の車を所有しています(地方の中小都市では世帯保有率・複数保有率ともに8割超)。
- 特に共働き家庭では夫婦それぞれが通勤に車を使う必要があるため「1人1台」体制も珍しくありません。地方在住でも鉄道網が整った地方都市(例:県庁所在地など)では車なし生活も可能な場合がありますが、それでも都市部に比べれば車の利便性は高く、また地方では駐車場代が安価(場合によっては自宅敷地内駐車で無料)なため車を持つハードルは低いと言えます。
自動車を所持する場合に発生するコスト
初期費用(購入費用)
- 車両本体の購入代金が最大の出費です。新車の場合、人気のコンパクトカーでも車両価格は約150~300万円程度になり、購入時には登録諸費用や税金(環境性能割など)も加算されます。
- ローンを利用すれば頭金次第で月々の支払いにできますが、ローン金利も実質コストであり、支払総額は現金一括より増加します(例:300万円を年利2%・10年ローンの場合、総支払額は約331万円)。
- 中古車を選べば初期費用を大きく抑えられ、特に新車から数年落ちの車は割安で買えるためおすすめです(※初期登録から年数が経つと価格が下がるため)。例えばトヨタのヤリスを中古で約200万円と仮定すれば、新車より安く初期費用を抑えられます。
固定費(毎年かかる費用): 主な固定費は以下の通りです。
- 自動車税/軽自動車税: 毎年4~5月に支払う税金。排気量によって額が異なり、普通車(1.5Lクラス)で年間約30,500円、軽自動車なら10,800円程度が目安です。※初度登録から13年超の車は税額が約15%重くなります。
- 自動車重量税: 車両重量に応じて新車登録時および車検時に課税される国税。車検のタイミングで2年(新車時は3年)まとめて支払いますが、年あたりに均すと普通車で約16,400円/年程度です(エコカー減税対象車は軽減措置あり)。
- 自賠責保険料(強制保険): 法定の自動車損害賠償責任保険料。車検ごとにまとめて支払います(24ヶ月で約25,000円前後)が、年間では約12,000~13,000円程度です。
- 任意保険料: 対人対物補償などを含む任意加入の自動車保険。加入は事実上必須で、保険料は年齢・等級・補償内容で異なります。30代で車両保険ありの場合、年間6~8万円台が一つの目安です(若年層は高額になりがちで、ゴールド免許や無事故による割引で徐々に安くなります)。高級車に乗る場合は車両保険料が跳ね上がるため注意が必要です。
- メンテナンス費・変動費: 車の維持には走行に応じた費用も発生します。
- 車検費用: 新車3年後以降は2年ごとに受ける法定点検整備です。車検基本料に加え、自賠責保険料・重量税・整備代行料などがかかり、ディーラー車検だとコンパクトカーでも一回あたり10万円前後になることもあります(交換部品によって増減)。平均的には年あたり4~5万円程度を見込むと良いでしょう。
- 修理・消耗品交換: オイル交換やタイヤ・バッテリー・ブレーキパッド等の消耗品交換、故障時の修理費用です。新しい車ほど故障は少ないですが、年式が古くなるほど突発的な故障で費用が発生しやすくなります。年間平均2~3万円程度を積立てておくのが望ましいです。高級輸入車の場合、部品代や指定工場での整備が必要になる場合があり維持費が割高になります。
- ガソリン代: 燃料費は走行距離と燃費、燃料単価によります。例えば年間5,000km走行・実燃費15km/L・ガソリン@≈175円なら約55,000円/年のガソリン代です。平均的な走行距離(年間8,000~10,000km)なら、コンパクトカーで10万円前後/年が目安になります(燃費の良いハイブリッド車・軽自動車ならもう少し低減可能)。高速道路を頻繁に利用すれば別途有料道路料金の出費も考慮が必要です。
- 駐車場代: 自宅に駐車スペースがない場合、月極駐車場を借りる費用です。地域差が大きく、都市部では月数万円(例:東京目黒区で月約35,000円)になることもあります。一方、郊外や地方では月数千円~1万円程度、持ち家で敷地内駐車できる場合は実質無料です。コストシミュレーションではひとまず月1.2万円(年14.4万円)程度で計上する例が多いです。
以上を合計すると、マイカー維持費は年間数十万円規模になります。例えばコンパクトカー(排気量1.5Lクラス)で年間約43万円(月あたり約3.6万円)が一つの目安です。下表は車種別の概算維持費の一例です(駐車場代12,000円/月で算出)。
| 費用項目 | 軽自動車(年間) | コンパクトカー(年間) | 大型車(年間) |
|---|---|---|---|
| 自動車税等 | 約10,800円 | 約30,500円 | 約43,500円 |
| 重量税(年換算) | 約12,300円 | 約16,400円 | 約16,400円 |
| 自賠責保険料 | 約12,422円 | 約12,806円 | 約12,806円 |
| 任意保険料 | 約80,000円 | 約85,000円 | 約90,000円 |
| 車検代(年換算) | 約25,000円 | 約25,000円 | 約25,000円 |
| メンテナンス費用 | 約15,000円 | 約18,000円 | 約20,000円 |
| ガソリン代 | 約81,000円 | 約101,000円 | 約135,000円 |
| 駐車場代 | 約144,000円 | 約144,000円 | 約144,000円 |
| 年間合計 | 約38万円 | 約43万円 | 約49万円 |
| 月平均 | 約3.2万円 | 約3.6万円 | 約4.1万円 |
※上記はあくまで目安であり、実際の費用は車種・利用状況によって増減します。例えば駐車場代は地域によって大きく異なりますし、ガソリン代も走行距離次第です。高級車では税金・保険・消耗品費用が軒並み高額になり、維持費が更に数割増になる点にも留意が必要です。
車を持たない場合の代替手段と費用比較
マイカーを所有しない場合でも、移動ニーズに応じて様々な代替手段があります。それぞれの特徴と費用感を比較します。
公共交通機関(電車・バス)
- 都市部では最も現実的な代替手段です。定期券を利用すれば月額数千~1万円台程度で日常の通勤通学が可能です。例えばJRや地下鉄の通勤定期券は区間にもよりますが月1~2万円以下で収まるケースが多く、自家用車の月間維持費より大幅に安価です。
- 加えて、都市部では深夜まで運行する路線も多く、時間帯によっては車より速く移動できるメリットもあります。ただし、大きな荷物や小さな子供連れの移動では不便を感じる場面もあるでしょう。
- その際はタクシーやオンデマンド交通(ライドシェア)が補完的役割を果たします。タクシー料金は初乗り数百円+距離料金で、短距離なら1000円台、郊外への長距離移動では数千円~1万円以上かかりますが、必要なときだけ利用するのであれば車を所有するより安くつく場合が多いです。特に都市部では「普段は公共交通+必要時にタクシー」で十分生活できる例も多く見られます。
カーシェアリング
- 近年普及した「必要なときだけ車を使う」サービスです。会員登録しておけば無人のステーションから15分単位で車を借りられます。料金は時間料金+距離料金が基本で、例えばタイムズカーシェアではベーシッククラスで15分あたり220円(1時間880円)、6時間以内の短時間利用なら距離料金(1kmあたり20円)が無料になるプランがあります。
- 月額基本料(数百円)は利用料金に充当されるため、使った分だけ払うイメージです。費用比較: カーシェアは使い方によりますが、例えば「毎週末に4時間、月1回遠出12時間」というモデルケースでは年間約28.2万円の費用試算となっています。これは1ヶ月あたり2.3万円程度で、前述のマイカー維持費(3~4万円/月)よりも割安です。
- つまりカーシェアなら維持費込みで月2~3万円で様々な車に乗る自由を得られ、マイカーより経済的な選択になりやすいことがわかります。
- カーシェアのメリットは維持管理(車検や保険)はサービス提供側に任せられる点で、利用者はガソリン代程度(※多くのサービスは料金にある程度含まれます)を負担するだけです。ただし、近隣にステーションがない地域では不便、長時間・長距離の利用では割高になる、といったデメリットもあります。
レンタカー
- 数時間~数日単位で車を借りる伝統的なサービスです。旅行や出張、大きな荷物運搬などまとまった時間車が必要な場合に適しています。費用は車種と時間によりますが、例えばコンパクトカー(トヨタ・ヤリス等)を24時間借りる場合、約7,000~9,000円/日程度が相場です(別途任意保険料込みの安心パック料金を含めると1日あたり1万円弱)。
- 週末だけレンタカーを使う生活では、月4回利用で約3.9万円、年間約46万円という試算になります。この額は短期的にはマイカー購入より安いですが、長期的(5年以上)には購入した方が支出総額が少なくなるケースもあります。
- つまりレンタカーは必要な期間だけ車を持てる柔軟性がメリットですが、継続利用するとコストが嵩むため、マイカー購入との損益分岐は利用頻度と期間によると言えます。
以上のように、車を持たない場合でも交通手段を組み合わせることで生活は可能です。都市部在住で普段は電車通勤の人なら、「日常は公共交通+休日にカーシェア/レンタカー」という形で不便を最小限にできますし、実際その方が支出が少なくて済む例が多いです。
地方在住でも、近年は地方自治体や民間でオンデマンド交通サービスが整備されつつあり、必ずしも自家用車に頼らない選択肢も増えています。ただし、完全な車なし生活には地域差があるのも事実で、特に地方の郊外ではまだまだ自家用車の利便性に勝る手段は少ないため、居住地の交通環境に応じた判断が必要です。
費用比較のまとめ
マイカー所有は毎月数万円の固定費が発生するのに対し、カーシェアや公共交通は使う分だけ支払うため、うまく代替できれば浮いた分を貯蓄・投資に回せる利点があります。公務員向けのシミュレーションでは、「東京で50年間マイカー所有 vs. カーシェア利用」で約2,500万円もの支出差が生じると試算されており、これは車関連費を投資運用に回すことで将来数千万円規模の資産を築ける可能性を示唆しています。このように代替手段を賢く使うことは、単に節約というだけでなく長期的な資産形成に大きな影響を与える戦略と言えるでしょう。
車を資産形成の妨げにしないための工夫
どうしても車が必要な場合や、ライフスタイル上マイカーを持つ選択をする場合でも、いくつかの工夫で家計や資産形成への悪影響を軽減できます。
車種・購入方法の工夫
- 無理なく維持できる手頃な車種を選ぶことが重要です。高級車や大排気量車は購入価格だけでなく税金・保険・燃費など維持費も高額になるため、収入に見合わない「背伸び」は禁物です。移動手段と割り切るなら中古車や安価な新車で十分目的を果たせます。特に中古車は初期の減価が進んで割安になっており、賢く選べば数年落ちで新車の半額程度という掘り出し物もあります。
- また日本では軽自動車やコンパクトカーのリセールバリュー(再販価値)が高い傾向があり、将来売却する可能性があるならそうした車種を選ぶとトータルコストを抑えやすいです。購入時には、可能であれば現金一括や頭金を多めに入れるなどしてローン元本を減らしましょう。
- ローンを組む場合も低金利ローンを選び、余裕ができれば繰上返済するなどして支払利息を最小限に抑える工夫が有効です。ローン返済が家計を圧迫するとその間の資産形成余力が削がれてしまうため、月々の返済額は収入の中で無理のない設定にすることが重要です。
維持費節約の工夫
- 維持費を抑えるために燃費や税額の低い車を選ぶのも手です。ハイブリッド車や電気自動車などは購入時の補助金や税制優遇が受けられる場合があり、長期的な燃料代節約と合わせて有利です(もっとも車両価格自体が高めなので総合的な損得勘定は必要)。また、日頃から定期メンテナンスを怠らず行いましょう。オイル交換やタイヤの空気圧点検をしっかりするだけでも燃費悪化や部品摩耗を防げ、ひいては大きな故障を未然に防ぎ修理代を節約できます。
- 自分でできる範囲のケア(洗車時のチェック等)を習慣づけ、消耗部品は早め早めに交換することで、車を常に良好な状態に保ちましょう。良い状態を維持することは車の価値下落を緩やかにする効果もあります。
買い替えタイミング
- 日本では初度登録から13年を超える車には自動車税・重量税の重課(約15~20%増)が課されます。古い車は燃費も悪くなり故障リスクも高まるため、維持費が膨らみがちです。したがって「壊れるまで乗り潰す」よりは、増税期限を一つの目安に一定年数ごとに乗り換える方が結果的に負担増を防げるケースがあります。特に走行距離が伸びやすい方や、古い車に乗り続けて高額な修理や燃費悪化に悩んでいる場合は、早めの買い替えを検討する価値があります。
- 一方で、買い替え自体にもお金がかかるため、現状で大きな不具合がなく年間走行も少ない場合は無理に買い換えず長く乗って元を取る方が得なケースもあります。この判断は車種・使用状況によりますが、共通して言えるのは「古い車をダラダラ維持すると想定外のコスト増リスクがある」という点です。
- 買い替え時には下取り査定がつくうちに手放すことで、次の車の購入資金に充当できるメリットもあります。リセールバリューが高いうちに売却し、新しい低コスト車に乗り換えるのも一つの戦略です。
経費計上・副業利用
- もし自家用車を仕事用途(事業用や副業用)で使うのであれば、関連費用の一部を経費として計上することで節税に役立てられます。個人事業主やフリーランスで業務利用する場合、ガソリン代や駐車場代、修理代はもちろん、自動車税や重量税ですら按分次第で経費にできると認められています(プライベートと業務利用を区別して按分計算)。
- 減価償却費(車両購入費)も耐用年数に応じて費用化でき、結果として所得税・住民税の課税所得を減らす効果があります。副業であっても条件を満たせば同様に車関連費を経費算入可能です。例えば副業で配送業務をするために車を使う場合、走行の割合に応じて燃料費や保険料を経費落としできます。
- 会社員でも業務上の必要経費(例:職務命令で自家用車を使った場合のガソリン代等)は確定申告で一部控除対象になるケースがあります。車を「お金を生む道具」として位置づけ、その費用を税優遇できるよう工夫すれば、完全な支出ではなく事実上手元資金を圧迫しない運用も可能になります(※ただし無理な経費計上は税務上認められないので専門家に相談を)。
副収入化やシェア
- 車自体を収益源にする発想もあります。たとえば普段使っていない時間帯にカーシェアサービスで個人の車を他人に貸し出す(ピーク時の需要に応じてマッチング)ことで収入を得る仕組みも登場しています。また、広告ステッカーを貼って走行することで報酬を得るサービス等、車を活用した副収入の選択肢も存在します。
- こうした取り組みは現時点で大きな収益にはなりにくいですが、「持っている車を遊ばせず、少しでもお金を生む方向へ活用する」ことで資産形成の足かせを軽減できます。家族や近隣で車を共同所有しシェアするのも費用負担を分担する一つの方法です。
- 以上のように、購入段階~維持・活用段階の工夫次第で車による資産形成へのマイナス影響を抑えられます。要は「いかに支出を最適化するか」です。車は放っておけばお金が出ていく存在ですが、その出費を賢くコントロールし、場合によってはリターンを生む手段に変えることで、資産形成と両立させることも不可能ではありません。ポイントは収入とのバランスを守ることと、車の支出に見合う価値(便利さや収益)を引き出すことです。
ライフスタイル別:車を持つべきかの適正判断基準
個々のライフスタイルや家族構成によって、車の必要性・経済的妥当性は異なります。以下、代表的なケースごとに判断ポイントを整理します。
単身(独身)者
- 都市部で一人暮らしの場合、基本的に車無しでも生活は成り立つケースが多く、経済面だけ見れば無理に所有する必要は低いです。特に平日は仕事で運転せず、週末のお出かけ程度でしか使わないなら、カーシェアやレンタカーで十分でしょう。
- 実際、都市部の若年単身層では「公共交通で十分」という意見が半数以上を占め、自家用車保有意向は2割未満という調査結果もあります。一方、地方で独身の場合は通勤や日常移動の足として車が必要な場面が多くなります。特に就職先が郊外にある場合や、買い物環境が車前提の地域では、生活の質を保つために車が実質必須となるでしょう。
- その場合でも、独身であれば軽自動車や中古コンパクトカーなど身の丈に合った経済的な車を選ぶことで、将来の資産形成に与える影響を抑えることが大切です。年収が低い段階で背伸びした車を買うと貯蓄ができず、資産形成が進まなくなる懸念があります(「年収400万円程度で車を持つと、どうやって資産形成しているのか不思議」という声もあるほどです)。独身時代は無理に車を持たず、その分の資金を自己投資や貯蓄に回すという選択も十分合理的です。
夫婦(二人暮らし)
- 子供がいない夫婦の場合、車の必要性は住む場所や生活パターンによります。都市部の共働き夫婦で職場が都心にあるなら、通勤は電車で済みますし、週末のお出かけも公共交通+タクシーで代用可能なことが多いです。そのため「マイカー無し夫婦」も増えています。
- むしろ駐車場代やローン返済で生活費を圧迫するより、浮いたお金を住宅購入資金や将来の教育費準備に回す方が堅実との考え方です。一方で郊外~地方在住の夫婦では、生活圏によって車が1台あると便利さが大きく向上します。特に買い物の足として、夫婦でどちらかが運転できるように車を持つケースが多いです。
- ただし二人暮らしであれば基本的に車1台で共有できるため、必要なときだけ使う運用もしやすいです。例えば夫が平日通勤で使い妻は休日に買い物で使う、といった調整が可能なら台数を増やさず1台で済ませる方が経済的です。夫婦ともにリモートワーク主体で在宅時間が長い場合、日常的な車利用頻度は低くなるため、敢えて所有せず必要時にカーシェアするという選択も現実的でしょう。
- 将来的に子供を持つ計画があるなら、その時に備えて購入を検討する手もあります(子供が生まれると生活スタイルが大きく変わるため、必要性も再評価すべきです)。いずれにせよ夫婦だけなら生活パターンを工夫して車なしでも十分やっていけることが多く、家計へのインパクトと利便性向上のバランスを見て決めると良いでしょう。
子育て中の家庭
- 小さな子供がいると車の利便性が飛躍的に高まる場面が多々あります。例えば子供の体調不良時に深夜に病院へ行く、大量の荷物を持ってベビーカーごと移動する、雨の日に保育園へ送り迎えする、といったシーンではマイカーがあると圧倒的に楽で安心です。
- 都市部でも、子育て中だけは車を所有する家庭もあります。ただ、その便利さと引き換えにコスト負担も増えるため悩みどころです。「車があれば確実に生活は便利になるが、安易に生活レベルを上げて良いものか」という葛藤を感じる親御さんもいます。
判断基準
- 子供の人数や年齢、生活圏で決まります。例えば都心部で徒歩圏に病院・公園・スーパーが揃っている場合、タクシーやデリバリーで乗り切れる場面も多く、必須ではないかもしれません。
- 一方、郊外で子供を複数抱えている場合、保育園・学校の送迎や習い事の送り迎えにも車が活躍します。実用性から言えば「子供2人以上+郊外在住」なら車1台(ミニバン等)があると生活が円滑になりやすいです。家計面では、子育て期は教育費や生活費も増える時期なので、車にかける予算を決めて無理のない範囲の車種を選ぶことが肝心です。
- またチャイルドシートの設置等を考えると車内空間が広めの車が望ましく、必然的に維持費も上がるため、他の支出とのトレードオフを考えましょう。子育て家庭では安全性も重視事項なので、維持費節約のために無理に古い車に乗り続けるより、適切にメンテナンスされた車に乗る方が結果的に安心です。なお、子供が大きくなれば車の使い方も変わるため、ライフステージの変化に合わせて必要性を見直すことも大切です。
リモートワーク主体の人
- 在宅勤務中心で通勤の必要がない人は、日常的な車利用頻度が低くなりがちです。都市部×リモートワークなら、週に一度買い物に行くかどうか程度で、タクシーやカーシェアで充分賄える場合もあります。そのため「リモートワーカーは車無し」が合理的にも思えますが、一方で在宅だからこそ郊外に居住するケースも増えています。
- 郊外や地方で自然環境の中で暮らしつつ在宅勤務をする場合、日々の買い物や子供の送り迎えなどで結局車が必要ということもあります。判断ポイントは、自宅周辺の日常生活インフラと、ご自身や家族の外出頻度です。リモートワークであっても時折オフィスや取引先に出向く必要がある人は、その際に車があれば感染症リスク回避や時間短縮になる利点もあります。
- また在宅時間が長い人ほど気分転換のドライブやワーケーション的な遠出をしたくなることもあり、趣味用途で車を持つ価値を見出す人もいるでしょう。このようにリモートワーク主体だから即「車不要」とも言い切れず、生活圏と行動パターンに応じて柔軟に判断すべきです。
- 総じて言えば、「平日日中は運転しないが休日にはアウトドアに出かけたい」というタイプなら車があると充実したライフスタイルを送れるでしょうし、「外出自体が月に数回」というタイプなら所有せず都度レンタカーの方が合理的でしょう。資産形成的には、使用頻度に見合わない車は固定費の無駄になるので、使う機会が少ないなら見栄で持たない勇気も必要です。
地方の共働き家庭
- 地方で夫婦とも働いている場合、通勤手段として一家に車2台体制も珍しくありません。特に職場が互いに反対方向だったり勤務時間がずれている場合、1台を共有できず2台必要になるケースが多いです。この場合の負担は、単純計算で維持費も2倍近くになります。ただし夫婦で車種を使い分けることで節約は可能です。
- 例えば「夫は通勤距離が長いので燃費重視の軽自動車、妻は子供の送迎があるのでミニバン」といった具合に、それぞれ用途に最適な車を選ぶことで無駄を減らせます。また2台必要でも両方新車にせず1台は中古にする、あるいはディーラーのメンテナンス契約を活用して故障リスクを下げるなど、家計に見合ったプランニングが求められます。
- 地方では公共交通が脆弱なため選択肢が限られますが、最近は職場の送迎バスや地域の相乗りタクシーなど取り組みもあるので利用可能なら検討しましょう。経済面では、2台持ちであっても住宅ローンや教育費との両立を図る必要があります。
- 車関連費が家計を圧迫しすぎないよう、家計全体の予算配分の中で車にかける適正額を決め、それ以上はかけないよう意識することが重要です。共働きで収入が二馬力あるとはいえ、車2台分の維持費(年間80~100万円超になることも)は将来の貯蓄機会を奪う大きなコストです。
- そのため、例えばボーナス等で繰り上げ返済や投資をしつつ、普段の生活費は車2台含めて月収内でやりくりする、といった計画性が求められます。
持ち家の有無
- 住宅を持っているかどうかも車所有の判断に影響します。持ち家(戸建て)で駐車場付きなら、月々の駐車場代負担がなく比較的気軽に車を持てます。特に郊外の一戸建てでは駐車スペースが確保されていることが多く、「せっかくスペースがあるから車を置こうか」という心理も働きます。
- 逆に賃貸住宅で駐車場代が別途かかる場合、毎月の家賃に加えて数千~数万円を駐車場に支払う必要があり、トータルの住居関連コストが上昇します。例えば家賃8万円・駐車場1.5万円なら実質家賃9.5万円と同じで、これを数年払えば相当の出費です。
- したがって賃貸派の人は「その駐車場代を家賃上乗せとみなして住環境のグレードアップに使うか、または貯蓄に回すか」を検討するとよいでしょう。一方で地方では賃貸物件でも駐車場無料・車2台OKという所もあり、その場合は住宅事情が車所有のハードルになりにくいです。
- 結論として、駐車場代等を含めた住居+車のトータルコストが家計に占める割合を算出し、それが適切かどうかで判断することになります。持ち家だからといって無計画に高級車を買えば結局ローン負担で苦しくなりますし、賃貸でも工夫次第で車を安く維持する方法はあります。要は住まいと車にいくら割くかのバランスを各家庭の状況に合わせて決めるのがポイントです。
以上、ライフスタイル別に見てきましたが、共通するのは「車がもたらす利便性」と「維持コスト」のトレードオフをどう評価するかです。家族構成や収入、居住地域によってその評価は変わります。資産形成という観点では、可能な限り車への支出を最適化し、浮いた資金を投資・貯蓄に振り向ける方が望ましいですが、生活の質も無視できません。
自分たちの生活に本当に車が必要か?その費用に見合うメリットが得られるか?を定期的に見直し、状況が変われば柔軟に持つ/手放す判断をすることが大切です。ライフステージの移り変わりに応じ、車との付き合い方もアップデートしていきましょう。
資産形成への影響評価 – 車は「負債」か?
最後に、自動車所有が長期的な資産形成にどのような影響を与えるかを整理します。ポイントは、車が生み出すお金よりも、車に支払うお金の方が圧倒的に多いという事実です。
減価償却と価値下落
- 資産形成の文脈で語られる際、車はしばしば「減価資産」とも呼ばれます。購入直後から市場価値が下がり続け、年々その価値は減少するため、所有者は価値下落のリスクを負うことになります。新車で購入した場合、3年後には半値以下になることも珍しくなく、特に人気のない車種や高額車は下落幅が大きいです。
- つまり車は時間とともに目減りする資産であり、将来的に換金できるとはいえ購入額を回収することは難しいものです。この点で、値上がり益を期待できる金融資産や不動産とは対照的であり、基本的には「負債(将来の現金流出を生むもの)」とみなす方が適切でしょう。
- もちろん仕事で使って収入を生む車(営業車や配送車など)は間接的に稼ぐ手段ですが、自家用車単体ではお金を生まないため、資産形成には寄与せずむしろコストセンターとなります。
キャッシュフローへの影響
- 車を持つと、前述したように毎月かなりの固定費・変動費が発生します。この継続的な現金流出は、本来なら貯蓄や投資に回せたお金を食いつぶすことになります。
- 例えば年間40万円の車維持費は、手取り年収400万円の人にとっては手取りの10%に相当し、これを30年間続ければ単純計算で1200万円もの現金を使うことになります。実際には物価変動や所得増減がありますが、人生トータルで車にかかるお金は「家一軒分」に匹敵するとも言われます。
- ファイナンシャルプランナーの試算でも、車を生涯所有し続けるコストは数千万円規模にのぼる結果が示されています。例えば前述の試算では、東京でコンパクトカーを50年間所有すると約4,000万円の総支出になりました。これはちょっとした住宅ローンと同程度の負担です。車を持てばその分だけ他の用途に使える現金が減る――この機会損失は非常に大きく、資産形成を考える上で看過できません。特にローンで車を買った場合、利息分も含めて将来手元から出ていくお金が増えるため、資産を増やすどころか目減りさせる要因になります。
投資機会との比較(機会費用)
- 逆に言えば、車に使わなかったお金を投資運用に回せば大きな資産を築ける可能性があるということです。経済学で言う「機会費用」の観点ですが、車関連費に支出した1円は、資産運用に回せなかった1円でもあります。
- 例えば年間50万円の車コストを30年間インデックス投資(平均利回り5%と仮定)に回したとすると、30年後には元本1500万円に加え運用益で数百万円以上が得られる計算になります。前述のシミュレーションでは、カーシェアリングで節約できるお金を新NISA等で50年間運用したところ、約7,700万円もの資産に成長し得るとの結果も出ました。
- 極端なケースですが、「車を持たない選択」が老後資金を劇的に増やす可能性を示しています。もちろん実際の運用結果は不確実ですが、少なくとも車に消えてしまうお金には将来の増殖余地がないことは確かです。その意味で、「減価する資産(車)の管理は市場(カーシェア企業等)に任せ、自分は増価する資産の構築に集中する」という考え方が最も賢明な戦略だという指摘もあります。
- 車を所有しなければ、その維持費分だけ家計に余裕が生まれ、より早くから積立投資を始めたり、必要な保険に加入したりと健全な資産形成習慣を築きやすくなるでしょう。
例外的なケース
- 車そのものが資産価値を持つケースもごく一部にはあります。ヴィンテージカーや希少な旧車など、コレクターズアイテムとして時間とともに価値が上がる車も存在します。しかしこれらは趣味・投機の領域であり、一般的なマイカーとは切り離して考えるべきでしょう。
- また、車を使って収入を得ている人(営業職の成功報酬に寄与、配達で利益を生む等)にとっては、その車は事業投資とみなせますが、そうでない限り大半の人にとって車は消費財です。よって資産形成の文脈では、車はコストであり、投資対象ではないとの基本に立ち、いかにそのコストをコントロールするかが鍵となります。
まとめ
- 自家用車の所有は、便利さや人生の充実度を高めてくれる一方で、家計面では長期的な重荷(固定費)となりえます。資産形成を最優先に考えるならば、まず車にかかる支出を見直し、必要性が低ければ思い切って手放す、もしくは代替手段に切り替えることが推奨されます。
- どうしても所有する場合でも、上述のような工夫で支出を最適化し、「車貧乏」にならないよう注意が必要です。資産形成と車のバランスを取ることは、豊かな将来への戦略的選択と言えます。車との付き合い方次第で、経済的にも経験的にもより豊かな人生を送ることは十分可能です。あなたの資産形成計画に照らして、ぜひ最適な選択を検討してみてください。